
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


放課後等デイサービスを開業したい――そんな想いを胸に、この記事を読まれている方も多いのではないでしょうか。
「子どもたちの成長を支えたい」「地域に必要とされる場所を作りたい」
そんな情熱があれば、福祉経験がなくても一歩を踏み出すことができます。
この記事では、放課後等デイサービス(通称:放デイ)の開業を目指す法人設立予定の方に向けて、開業準備の流れから運営のポイントまで、わかりやすく解説します。
放課後等デイサービスは、障がいのある6歳~18歳の子どもたちが、放課後や長期休暇中に通う福祉サービスです。
支援の内容は多岐にわたります。
たとえば…
つまり、「家庭・学校・地域以外の、安心して過ごせる第4の居場所」です。
共働き家庭や、支援が必要なお子さまを抱えるご家庭にとって、放デイはとても大切な存在。需要は年々高まり、地域によっては「空き待ち」が出るほどです。
放課後等デイサービスの開業には、「児童福祉法に基づく指定」が必要です。個人では申請できないため、まずは法人の設立が第一歩です。
事業を始めるには、以下のいずれかの法人格が必要です。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 合同会社 | 設立が簡単。少人数・低コストで始められる。 |
| 株式会社 | 信用力が高い。将来的な事業拡大にも対応しやすい。 |
| 一般社団法人 | 非営利活動に向いているが、報酬を得ることも可能。 |
| NPO法人 | 社会的意義が高いが、設立に時間と手間がかかる。 |
迷ったら、「合同会社」か「株式会社」から始める方が多いです。専門家(行政書士・司法書士)に相談するのもおすすめです。
「この地域に放デイは足りているか?」「どんな特色が求められているか?」
自治体の福祉課、相談支援事業所、障がい児の家庭にリサーチしてみましょう。
中には「事業所が飽和しているため、新規指定は難しい」という地域もあります。開業エリアを選ぶ際は、事前に市町村に相談しましょう。
放デイに使える物件には、以下のような条件があります。
同時に、以下のような事業計画書を作成していきます。
計画書は、指定申請や融資申請にも必要になるため、信頼性の高い内容に仕上げましょう。
放デイを運営するには、市町村に「障がい児通所支援事業所」として指定を受ける必要があります。
申請から指定までには1~3か月程度かかるため、スケジュールには余裕を持ちましょう。
指定要件を満たすため、必要な職種は以下の通りです。
| 職種 | 条件 |
|---|---|
| 管理者 | 経営管理に精通している人(兼務可能) |
| 児童発達支援管理責任者 | 経験+研修修了が必要 |
| 指導員 | 教員免許、児童福祉経験、保育士など |
特に「児発管(じはつかん)」は重要ポジション。人材不足の地域もあるため、早めの確保がカギです。
放課後等デイサービスは、人と人との信頼関係で成り立つ仕事です。
発達の特性はさまざま。個性を尊重しながら、「できた!」の体験を積み重ねていきましょう。
家庭と連携し、安心して預けてもらえる関係を築くことが大切です。連絡ノートや面談などで、密なコミュニケーションを。
近隣住民への配慮、他機関との情報共有など、「地域に開かれた事業所」を目指すことが信頼につながります。
放課後等デイサービスの開業は、決して簡単な道ではありません。
けれど、あなたの想いが形になったその先には――
が、確かに生まれます。
準備に不安がある方も、まずは小さな一歩から始めてみましょう。
行政や専門家に相談することも大切なステップです。
あなたの勇気が、未来の支援の輪を広げていきますように。
応援しています!
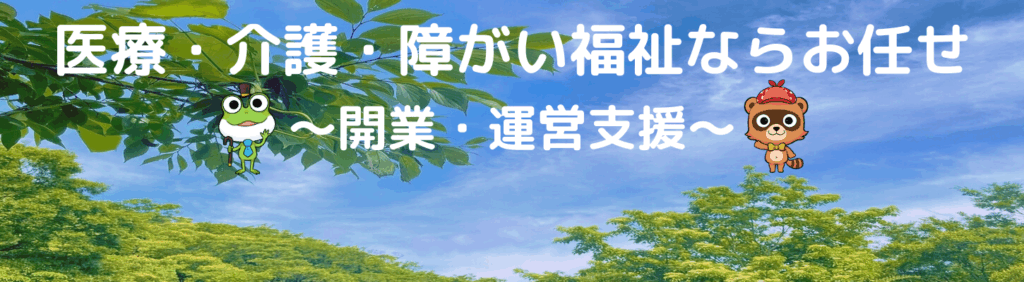
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートいたします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。