
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370

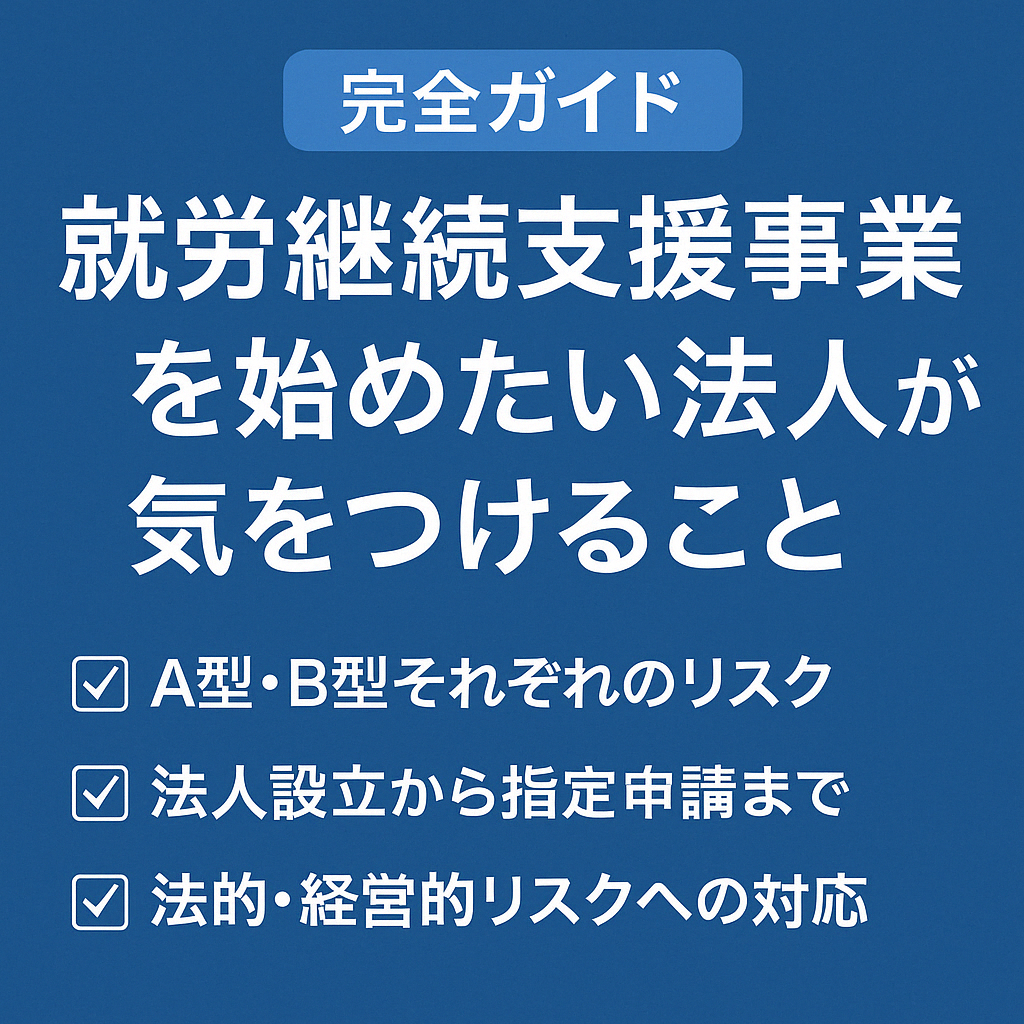
就労継続支援事業(A型・B型)は、障がいのある方の「働きたい」を支える重要な福祉サービスです。しかし、参入する法人にとっては「福祉」と「ビジネス」の両立が求められるため、事前に十分な準備と理解が不可欠です。
この記事では、これから就労継続支援事業を始めたい法人が特に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。
まず大前提として、就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
| 種別 | 主な対象者 | 雇用契約 | 報酬単価 | 利用者の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 比較的就労能力のある方 | あり(最低賃金) | 高め | 安定して働ける方 |
| B型 | 雇用が難しい方 | なし(工賃支給) | 低め | 就労準備段階の方 |
自社の理念や地域のニーズに合ったサービス形態を選ぶことが重要です。
就労継続支援事業を運営するには、都道府県または指定都市からの**「指定」を受ける必要があります**。そのためには以下の人員配置基準を満たす必要があります。
特にサビ管は実務経験と研修要件があり、事前の計画的な人材確保が必要です。
就労継続支援事業は、利用者数に応じた報酬制度ですが、特にA型では最低賃金の支払い義務があるため、安定した業務受注や生産活動が必要です。
事業継続が難しいと指定取消となるケースもあるため、経営視点が求められます。
指定後も定期的に「運営指導」や「実地指導」が実施されます。帳票整備・サービス記録・個別支援計画など、福祉事業としての正確な運営が求められます。
不備があると返還・指導・最悪の場合は指定取消になることもあるため、最初から仕組み作りが重要です。
利用者の集客や定着には、相談支援事業所や医療機関、特別支援学校との連携が欠かせません。また、事業所の独自性や得意な業務を打ち出し、地域に必要とされる施設を目指しましょう。
例:
就労継続支援事業の指定申請には、法人設立、物件確保、人員確保、運営規定の作成など、準備に最低でも3〜6ヶ月は必要です。
主な必要書類には以下があります。
就労継続支援事業は、障がい者の自立支援という社会的意義が高い一方で、継続的な経営が求められるハイブリッドな事業です。単に「想い」だけでは成立せず、福祉制度・会計・労務管理・業務獲得など幅広い視点が求められます。
これから始めようと考えている法人様は、ぜひ専門家や先行事例から学びながら、着実に準備を進めていきましょう。
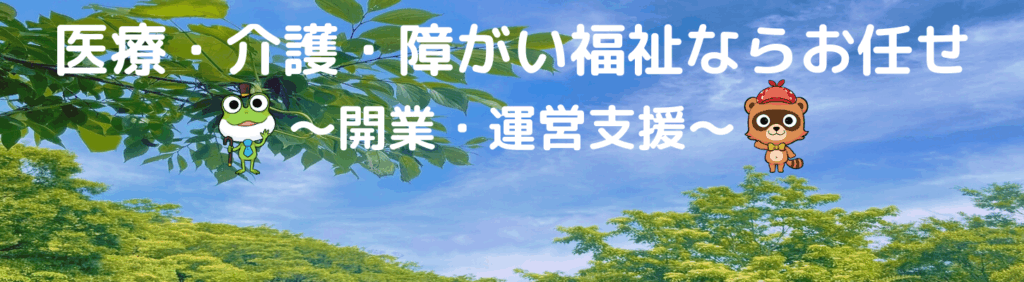
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。