
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370

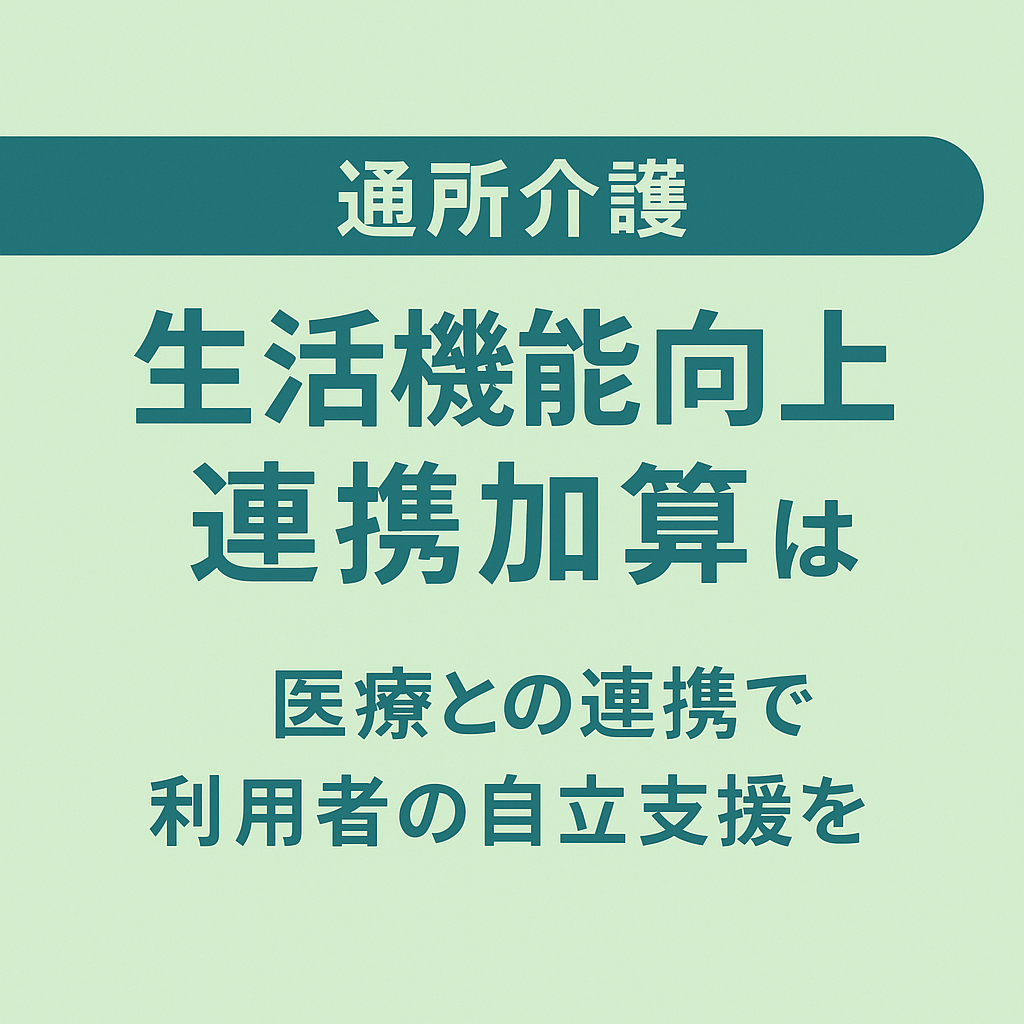
高齢化が進む日本において、介護サービスの役割は「生活の支援」から「自立支援・重度化防止」へと大きく転換しています。特に、通所介護(デイサービス)においては、要介護高齢者が住み慣れた地域でできる限り自立した生活を継続できるよう、医療・リハビリの視点を取り入れた支援が求められています。
そのような中で、重要な役割を果たすのが「生活機能向上連携加算」です。本加算は、通所介護事業所と医療専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)が連携し、利用者一人ひとりの生活機能をアセスメントし、支援計画の立案・評価・見直しを行う取り組みを評価するものです。
外部機関に所属している場合でも、契約を結んで連携を図れば加算対象となります。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| アセスメント | 専門職が利用者を直接評価し、心身機能・活動状況などを記録する |
| 個別計画の立案 | アセスメント結果に基づき、生活機能向上のための個別計画を作成 |
| 助言・評価 | 専門職が職員へ具体的な助言を行い、支援状況を評価・フィードバック |
| ケアマネとの連携 | 情報共有・共同支援の体制を構築(モニタリング含む) |
| 定期的な見直し | 少なくとも6か月に1回は再評価と計画の更新が必要 |
※上記の一連の流れを文書で記録・保管することが必須です。
| 加算区分 | 内容 | 単位数(月1回) |
|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 外部リハ職との連携(訪問なし) | 100単位 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 外部リハ職が定期訪問・助言を実施 | 200単位 |
※加算Ⅱでは、専門職が現場に訪問し、直接的な助言・評価・支援があることが条件です。
通所介護に医療専門職の視点を取り入れることで、単なる介護支援にとどまらず、個別性の高いプログラムが提供可能となり、機能訓練の実効性が高まります。
早期介入による生活機能の維持・向上は、施設入所や医療依存度の増加を防ぎ、在宅生活の継続に大きく寄与します。
制度への理解と実践が進んでいる施設は、家族やケアマネジャーからの信頼度も向上し、利用者確保・地域内での評価向上にもつながります。
Q. 外部のリハビリ専門職がいない場合はどうする?
→ 地域の訪問看護ステーションやクリニック、リハビリ事業所との連携が可能です。医師の指示のもとで協働できる体制を整えましょう。
Q. アセスメントや助言の内容はどう記録すればよい?
→ 厚生労働省や自治体が出している様式例を参考に、評価票・助言書・記録簿などを整備するとよいでしょう。
「生活機能向上連携加算」は、介護サービスに医療の力を取り入れることで、より質の高い支援を実現する取り組みです。
利用者の尊厳ある暮らしを支えるとともに、介護職とリハ職が互いの専門性を尊重し合いながら連携を深めることで、地域包括ケアの真の実現にもつながります。
今後、さらなる制度改定や報酬の変化も予想されますが、生活機能の維持・向上はいつの時代も重要課題。ぜひ積極的に本加算の導入を検討し、利用者と施設の未来をより良いものにしていきましょう。
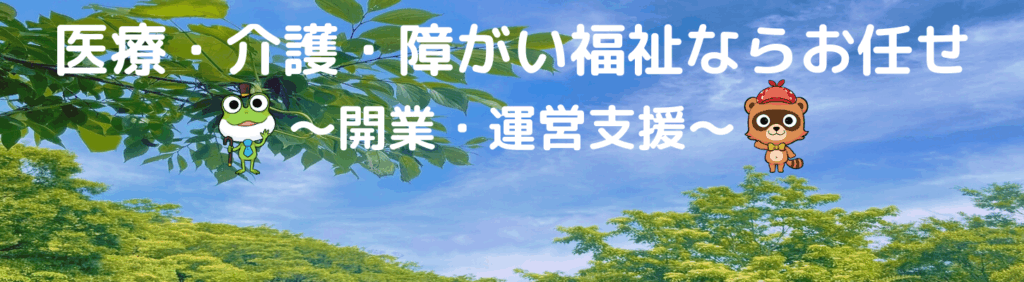
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。