
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370

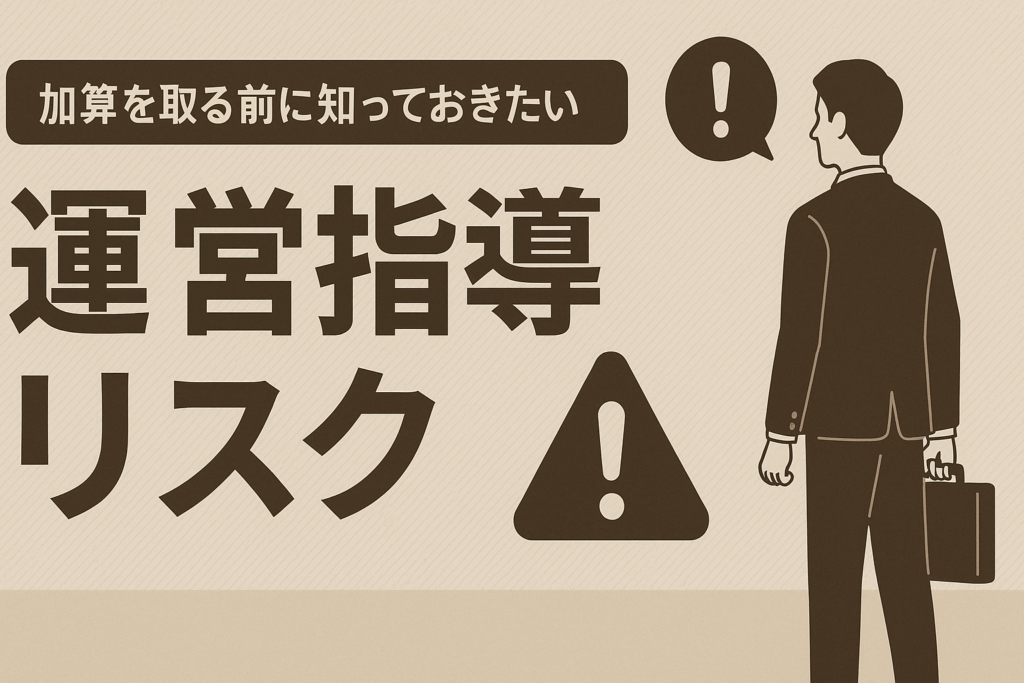
介護・障がい福祉サービス事業所の運営において、報酬改定のたびに話題となる「加算」。
体制整備やサービス向上に対する報酬として、加算を取得することは収益アップにもつながります。
しかし、加算取得は「プラス」ばかりではありません。
その裏側には、“運営指導”というリスクが存在することを忘れてはいけません。
加算を取れば取るほど、運営指導の際にチェックされるポイントは増え、場合によっては返還や是正指導の対象にもなり得ます。
この記事では、加算取得に潜む「運営指導リスク」とその回避方法について、現場目線で詳しく解説します。
「運営指導(実地指導)」とは、行政機関(都道府県・市区町村)が、福祉事業所の運営状況を確認し、法令や報酬算定ルールに違反がないかをチェックする制度です。
これらの中で、「加算を取得しているかどうか」は、重点的なチェック対象になります。
加算の算定には、それぞれ詳細な要件が定められています。
必要な記録や帳票が1枚抜けているだけでも、「算定要件を満たしていない」と判断され、返還対象になることがあります。
たとえば:
こうした場合、形式的に書類だけ整っていても、指導時に“実態がない”と判断され、厳しい指摘を受けます。
令和の制度改正では、加算に「研修実施義務」が伴うケースが増えています。
しかし実地では、「研修はやったつもり」でも、記録・写真・出席確認などがなければ評価されません。
「取れる加算はすべて取っておこう」という考えは、かえってリスクを拡大させる要因になります。
加算は、「取得後」が本番です。
制度要件の継続的な管理、職員教育、記録整備、定期的な内部点検ができるかどうかが大切です。
加算取得は、“体制が整っていることの証明”としての意味を持ちます。
実態が伴っていない場合、「不正請求」と判断されるリスクもあり、最悪の場合は指定取消や返還命令、自治体との信頼関係の破綻につながります。
以下の項目にすべて✅がつかない場合、加算取得は見送る勇気も必要です。
加算を正しく取得し、継続していくためには、運営指導の視点を持って日々の業務を見直すことが不可欠です。
日々の記録の蓄積が、運営指導における「最良の備え」となり、自治体から信頼される運営にもつながります。
事業所単独では判断が難しい場合は、行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、客観的な視点から加算取得の可否を検討することができます。
加算取得は「ゴール」ではなく、「適正な運営を続けるためのスタートライン」。
安心して加算を活用するためにも、運営指導の視点を持った備えをしておきましょう。
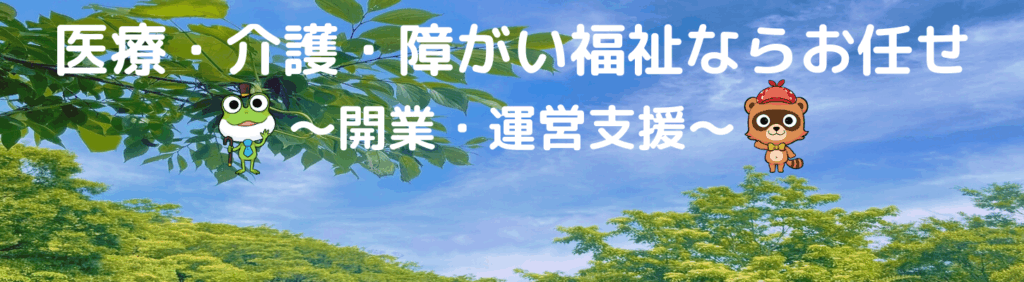
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。