
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370

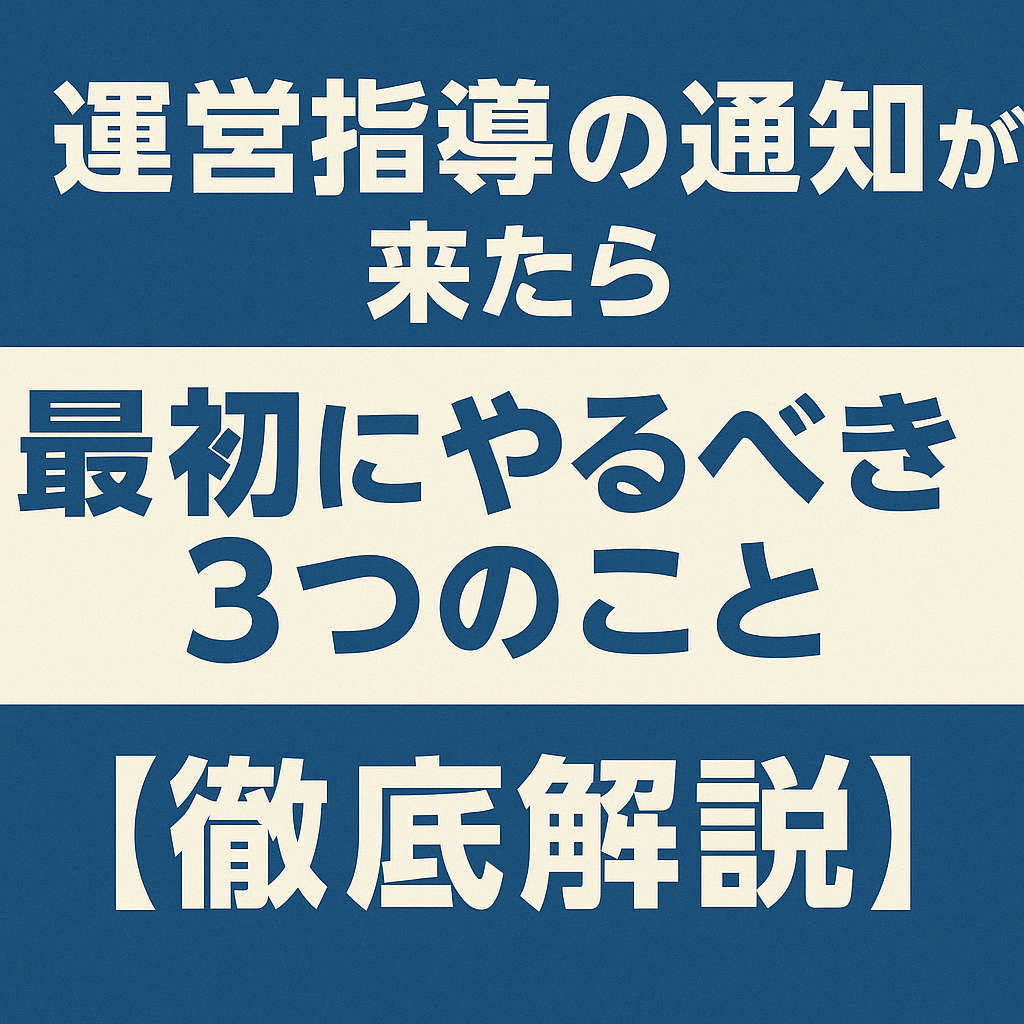
介護・障がい福祉サービス事業所において避けては通れない行政の監査のひとつが「運営指導」です。
この運営指導は、事業所の運営状況が法令や基準に適合しているかをチェックする重要な機会であり、適切に対応することで、事業所の信頼性や継続性にも大きな影響を及ぼします。
この記事では、運営指導の「通知」が届いたときに、まず最初にやるべき3つのステップを、わかりやすく・丁寧にご紹介します。慌てず、冷静に、そして確実に準備を進めましょう。
まず最初に行うべきことは、届いた通知書をしっかり読み込み、記載内容を正確に把握することです。通知書には、以下のような重要事項が記載されています。
この内容を確認しないまま準備を始めると、準備の方向性がずれてしまい、余計な手戻りが発生します。
通知書を確認したら、次にやるべきことは対応スケジュールの作成です。
実地指導までの限られた日数の中で、誰が・いつ・何を準備するのかを明確にし、職員全体で共有することが重要です。
例:
| 項目 | 期限 | 担当者 |
|---|---|---|
| 通知書の確認・内容共有 | 当日中 | 管理者 |
| 必要書類リストの作成 | 通知から2日以内 | サビ管・事務担当 |
| 書類収集・整理 | 指導の1週間前まで | 各担当 |
| 模擬面談の実施 | 指導の前日まで | 管理者・全職員 |
🔍 ポイント
実地指導の目的は「罰すること」ではなく、「適正な運営への指導」です。落ち着いて、計画的に準備することが成功のカギです。2.書類・帳票類の確認と整備を徹底する
● 書類は「見られる」ことを前提に整理する
運営指導で最もチェックされるのが、各種書類や記録です。普段の業務で記録している内容が、きちんと保管され、第三者が見てもすぐに理解できるように整っているかが問われます。
必要な書類の一例:
- 人員配置表・出勤簿(常勤換算などが適切か)
- 利用契約書、重要事項説明書、同意書
- 個別支援計画、モニタリング記録
- サービス提供記録(業務日誌、支援記録)
- 研修実施記録、虐待防止委員会・身体拘束委員会議事録
- 加算届出書、加算に関する記録や帳票
● 書類の保存状態と整合性を確認
書類があっても、
- 内容に矛盾がある
- 保存方法が不適切(バラバラ、紛失している)
- 電子的で閲覧困難
といった場合には「不備」と判断されることもあります。
印刷が必要な書類は紙に出力し、クリアファイルやインデックスで分類。誰が見ても一目でわかる状態を目指して整理しましょう。
3.職員との情報共有と役割分担を明確にする
● 職員の「意識」と「安心感」が現場力に
運営指導は、管理者や事務員だけが準備すれば良いものではありません。全職員が共通認識を持ち、自分の役割を把握していることが、当日の対応の質を大きく左右します。
- 運営指導の目的と流れの説明会を実施
- 指導当日の対応メンバーの役割分担(説明係、書類提出係、案内係など)
- よくある質問への回答練習(ロールプレイ)
「質問されると不安」という声は多く聞かれますが、事前に内容を共有し、練習しておけば安心です。
● 過去の指摘事項があれば職員と一緒に振り返る
以前の運営指導で何か指摘があった場合は、その改善内容も確認し、同じことを繰り返さないように注意が必要です。
おわりに|「準備8割」で運営指導は乗り切れる
運営指導は決して「脅し」や「罰」ではなく、適正なサービス提供のための機会です。準備をしっかり行えば、怖いものではありません。
通知が来たら、まずこの3つのステップを落ち着いて進めましょう。
- 通知内容の確認とスケジュールの作成
- 書類・記録の整備
- 職員との情報共有と役割分担
この3本柱を意識して、運営指導に万全の体制で臨んでください。
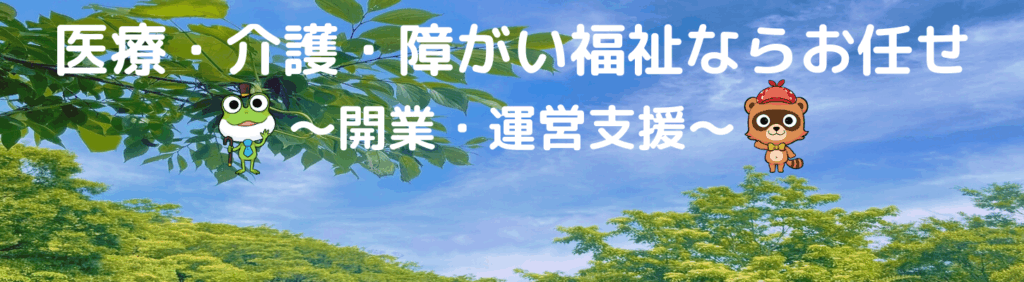
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。

当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。