
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


障がい福祉サービス事業を運営している皆さまにとって、「指定更新手続き」は避けて通れない重要な手続きです。更新申請を忘れていたり、準備が間に合わなかったりすると、最悪の場合、事業を一時停止しなければならないケースもあり、利用者や職員に大きな影響を与えてしまいます。
この記事では、障がい福祉事業に特化した行政書士の立場から、「指定更新手続きをスムーズに進めるためのポイント」について詳しく解説いたします。
障がい福祉サービス(例えば、生活介護・就労継続支援・放課後等デイサービスなど)は、一定期間ごとに「指定の更新申請」を行う必要があります。多くのサービスでは「6年に1度」の更新となっており、指定を受けた年月日から計算して6年目の前に申請を行わなければなりません。
申請期限を過ぎてしまうと、指定の空白期間が生じてしまい、最悪の場合「無指定状態」となり運営が一時停止されることも。
事業所の運営状況を証明する書類(実績報告、職員配置、運営規程、事業報告書など)を整理していなかったため、申請に時間がかかるケース。
制度改正により、指定基準や運営基準が変更されている場合があります。古いままの規程や体制で更新を申請すると、不備として返戻されるリスクがあります。
更新申請の受付開始時期(通常は有効期限の3〜6か月前)を必ず確認し、職員体制や帳簿、必要書類の整理を計画的に始めましょう。
👉【アドバイス】自治体の福祉課に確認すれば、更新予定事業所には通知が出される時期を教えてもらえます。
厚生労働省からの通知や、地方自治体のホームページには指定基準・運営基準の変更点が公開されています。更新申請時に「最新基準に適合しているか」を必ずチェックしましょう。
更新申請で提出が求められる代表的な書類は以下の通りです:
書類の不備は申請の遅延につながるため、早めに揃えましょう。
申請直前ではなく、半年ほど前に「内部監査」のようなかたちで自己点検を行うと、見落としや改善点を早期に発見できます。
指定更新は、「ただ書類を揃えるだけ」では済みません。運営状況の確認や記録整備、基準適合性の確認など、多くの専門的な知識が必要になります。
障がい福祉に特化した行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります:
事業者さまは、本来の支援業務に集中しながら、安心して更新手続きを進められます。
障がい福祉サービス事業の運営において、指定更新手続きは極めて重要な節目となります。余裕を持って準備を始め、正確な情報に基づいて手続きを進めることが、利用者への安定した支援を継続するための鍵です。
もし「手続きに不安がある」「自治体とのやり取りに慣れていない」と感じる場合は、専門家である行政書士にぜひご相談ください。スムーズで確実な更新を、全力でサポートいたします。
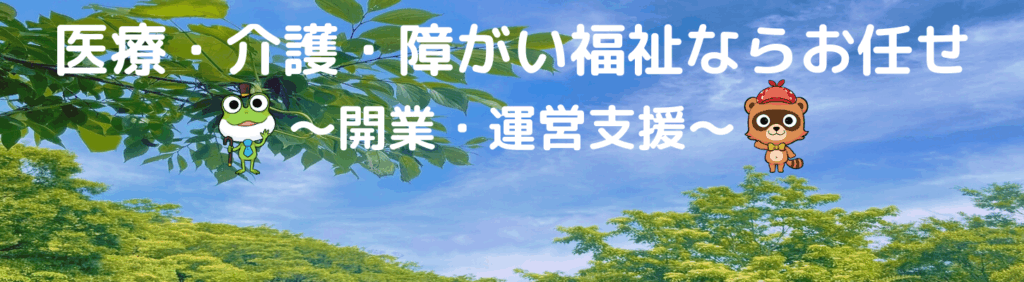
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。

当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。