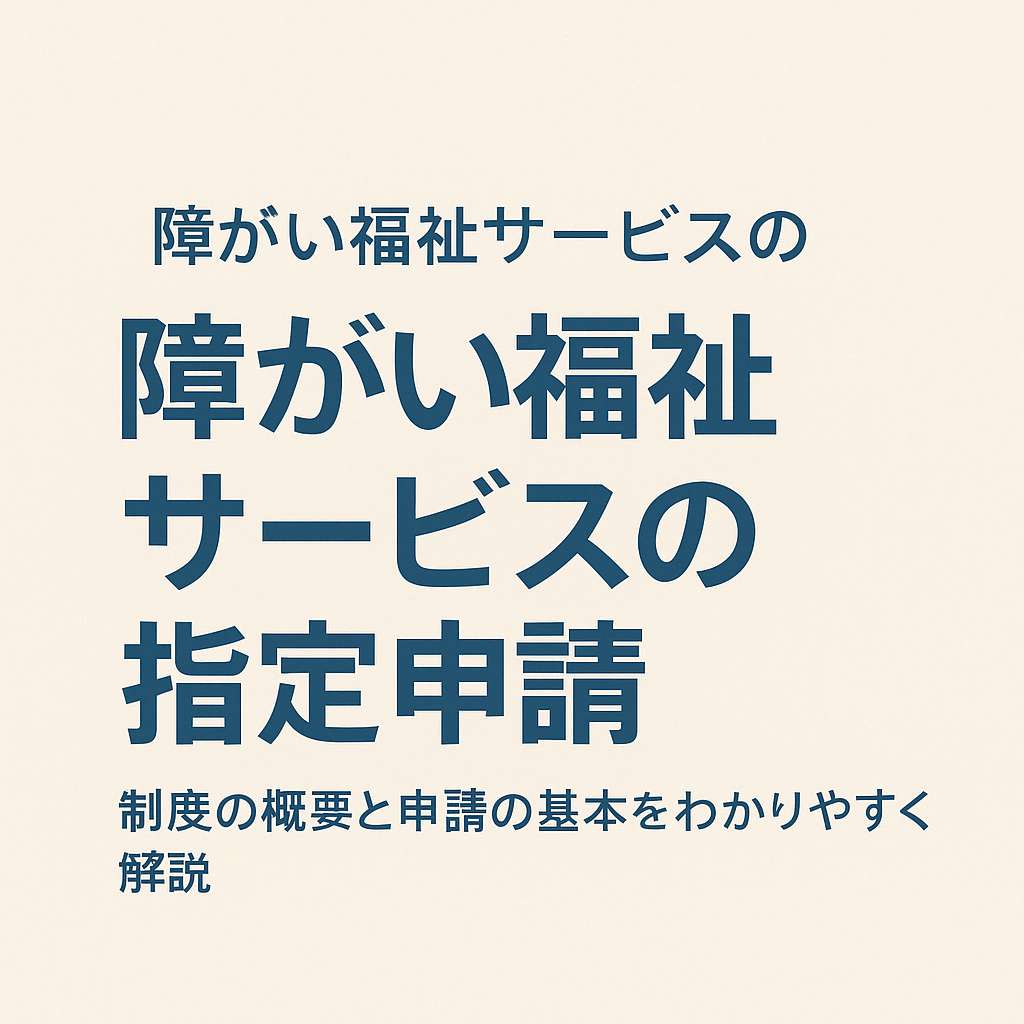
障がい者総合支援法や児童福祉法に基づき、福祉サービスを提供するには、国や地方自治体からの「指定」を受ける必要があります。
この指定を受けることにより、初めて公的な障がい福祉サービスとして、利用者からの給付費(報酬)を請求できるようになります。
■ 指定の目的
- サービスの質を一定以上に保つため
- 利用者保護の観点から事業者を審査するため
- 不正請求や基準違反を防ぐための仕組み
対象となる障がい福祉サービスの種類
障がい福祉サービスには、以下のような種類があります。どのサービスを提供するかによって、申請先や基準も異なります。
主なサービス例:
- 就労継続支援A型・B型
- 生活介護
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所
- 居宅介護・重度訪問介護
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援 など
指定申請の基本的な流れ
- 法人設立(株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など)
- 事業所物件の確保(用途・面積など基準に合ったもの)
- 人員の確保(管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者など)
- 運営体制や書類の準備(運営規程、契約書、従業者の資格証明など)
- 自治体への事前相談・指定申請書の提出
- 審査・補正対応
- 指定通知書の交付 → 事業開始
申請先はどこ?
- 市町村指定(児童系サービス):放課後等デイサービス、児童発達支援 など
- 都道府県指定(障がい者向けサービス):就労支援、生活介護、共同生活援助 など
※自治体によって異なります。
地域によっては、「指定受付は○か月前まで」などの期限があるため、必ず事前に担当部署に確認することが重要です。
指定申請でよくある注意点
- 書類に不備があると「補正依頼」が発生し、審査が長引く
- 職員配置や資格が基準を満たしていない
- 法人登記内容と提出書類の名称・住所が一致していない
- 事業開始日から逆算してスケジュール管理ができていない
指定申請は専門家に相談するのも有効
行政書士などの専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります:
- 書類の不備を防げる
- 手続きにかかる時間を短縮できる
- 自治体とのやりとりをスムーズに進められる
- 開業スケジュールを確実に立てられる
まとめ
障がい福祉サービスの指定申請は、サービスの提供を始める上で最も基本かつ重要なステップです。要件や流れをしっかり理解し、計画的に準備を進めることが成功のカギとなります。自治体のガイドラインや相談窓口を活用しつつ、必要に応じて専門家のサポートも検討しましょう。

