
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


障がいのある方やご家族から、「障がい者手帳を取ると、どんなメリットがあるの?」「取得したら何か制限があるの?」というご相談をよくいただきます。
今回は、障がい者手帳を取得することで得られる支援や制度利用のメリット、そして注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。
障がい者手帳とは、障がいのある方が福祉サービスや支援制度を受けるための公的な証明書です。
種類は大きく3つに分かれています。
それぞれ、障がいの種類や程度に応じて等級が定められ、利用できる制度や支援内容が異なります。
手帳を取得することで、自治体や国が提供する福祉サービスを利用できます。
たとえば、
これらは手帳の等級や障がい特性に応じて利用可否が決まります。
所得税や住民税、相続税などで障がい者控除を受けることができます。
また、自動車税や軽自動車税の減免、相続時の基礎控除の拡大など、経済的な負担を軽減する制度が多くあります。
JRや私鉄、市営バスなどで運賃の割引制度があり、本人や介護者も対象になる場合があります。
さらに、NHK受信料や携帯電話料金、公共施設の利用料の減免もあります。
障がい者雇用枠での就職活動や職場定着支援を受けやすくなります。
ハローワークや就労支援事業所と連携し、自分の特性に合った働き方を見つけるサポートが受けられます。
手帳の交付にあたっては医師の診断書などを提出し、障がいの状態が公的記録として残ります。
就職・進学などで手帳の提示を求められる場合もあるため、取得前に目的を明確にしておくことが大切です。
特に精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要です。
期限切れで割引や控除を受けられなくなることもあるため、更新時期は必ず確認しておきましょう。
同じ手帳でも等級によって受けられる制度が違います。
たとえば、身体障害者手帳の1級と6級では、利用できる福祉サービスや減免制度に差があります。
高槻市では、障がい福祉課(市役所本館1階)で申請を受け付けています。
医師の診断書、写真、印鑑、本人確認書類などが必要となります。
障がい者手帳は、生活の安定や社会参加を支えるための大切な制度です。
しかし、手帳を取得すればすべてが自動的に解決するわけではなく、どの支援をどのように活用するかを理解することが重要です。
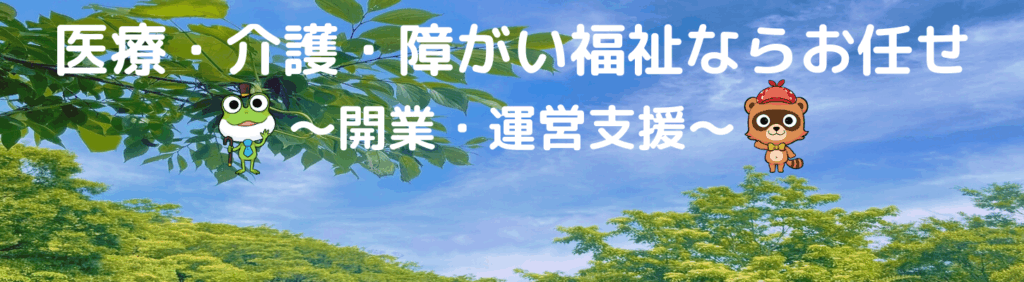
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。