
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


「コンプライアンス(Compliance)」とは、一般に「法令遵守」と訳される言葉ですが、福祉分野においては単に法律を守るという狭義の意味だけではなく、倫理的規範・社会的ルールを含めた広い意味での“信頼される行動”を指します。
福祉事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法、労働基準法、個人情報保護法など、多岐にわたる法令のもとで運営されています。これらの法令だけでなく、利用者やその家族、地域社会からの信頼に応えることもまた、重要なコンプライアンスの要素です。
福祉サービス事業は「人」に密接に関わる事業であるため、コンプライアンス違反が直接的に「人権侵害」や「信頼喪失」につながる可能性があります。以下に主な運営リスクを挙げ、それぞれの内容を詳しく解説します。
加算要件の誤解、実地指導での虚偽報告、指定基準を満たさない人員配置など、重大な違反が見つかれば、加算返還や指定取消といった行政処分の対象となります。特に近年は運営指導の精度も高まり、形式的な運営では通用しない時代となっています。
職員の労働条件やメンタルヘルス管理が不十分な場合、離職率の上昇や労基署からの是正勧告につながります。また、ハラスメントや職場内トラブルが放置された場合、訴訟に発展するケースもあります。
利用者の個人情報は非常にセンシティブです。パソコンの紛失、メール誤送信などによる情報漏えいは、行政処分や損害賠償リスクにもつながります。
虐待、身体拘束、不適切な対応などが報告された場合、社会的信用の失墜は避けられません。支援の質の低下は、利用者の状態悪化やクレーム、家族からの不信感を招きます。
補助金・給付費の返還、資金繰りの悪化など、経営の安定性が損なわれれば、結果的にサービス提供の継続が困難になります。特に指定取消となれば再申請は容易ではありません。
一部の事業所では、支援記録を実際よりも水増しし、不正に加算を取得していたとして約800万円の返還命令と指定取消を受けました。職員には直接の指示がなかったものの、「黙認していた」ことが重く見られました。
送迎車両に利用者の記録を保管していたが、施錠されておらず盗難被害に。個人情報の流出により、家族や関係機関からの信頼を損ないました。
職員が長時間労働を強いられたとし、未払い残業代請求と過労による精神疾患で訴訟を起こしました。経営者は「福祉の現場だから仕方ない」との認識でいたことが社会的にも批判され、悪質事業所として報道されました。
リスクは「ゼロ」にはできませんが、予防と管理の仕組みによって「回避可能なリスク」に変えることができます。
管理者や経営者は、現場任せにせず、日常的に事業運営の健全性を確認する視点が重要です。
「知らなかった」「任せていた」は通用しません。リスクに気づきながら改善を怠れば、それは組織ぐるみの違反とみなされることもあります。
経営理念として「利用者と職員が安心して過ごせる場を守る」ことを掲げるのであれば、リスク管理=理念の実践とも言えます。
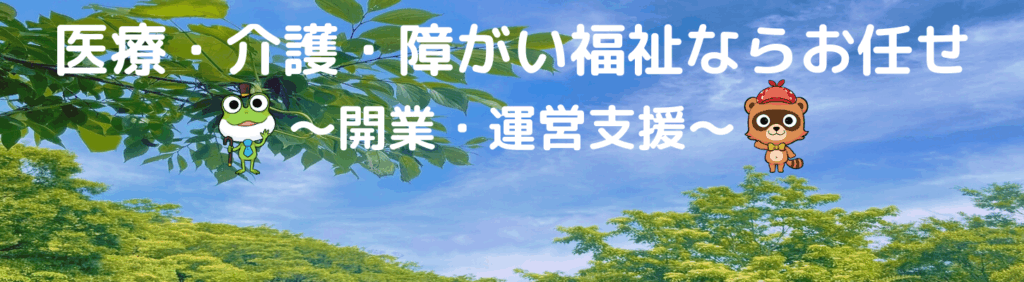
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。