
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


介護・障がい福祉サービスの現場では、利用者の写真を撮影する機会が少なくありません。
記録・モニタリング・広報・イベントなど、さまざまな場面で撮影が行われます。
しかし、個人情報保護の観点から適切なルールと手続きを踏まえていないと、思わぬトラブルや行政指導につながることもあります。
今回は、高槻市の介護・障害福祉専門行政書士が、写真撮影における個人情報保護と同意書の正しい取り方について詳しく解説します。
写真や動画には、利用者の「顔」「名前」「生活の様子」など、個人を特定できる情報が含まれます。
そのため、個人情報保護法の対象となり、適切な取得・利用・管理が求められます。
たとえば、
こうしたケースは、個人情報保護違反や苦情の原因となることがあります。
写真撮影を行う際は、まず「何のために撮影するのか」を明確にし、
利用者または家族にその目的を伝えることが重要です。
| 撮影目的 | 同意の要否 | 具体例 |
|---|---|---|
| サービス提供記録・モニタリング | 必要(原則) | 支援経過の記録、計画作成の参考など |
| 行事・イベント時の記念撮影 | 必要 | 夏祭り・外出支援・作品展など |
| 広報・ホームページ掲載 | 厳重な同意が必要 | HP、パンフレット、SNSなどへの掲載 |
| 研修・職員教育用 | 必要 | 介助技術やケーススタディの共有など |
※「撮影目的が異なる場合」は、目的ごとに同意を得ることが基本です。
口頭ではなく、書面(または電子署名)で明確に同意を得ることが原則です。
同意書には次の項目を盛り込みましょう。
認知症の方・知的障がいや精神障がいを持つ利用者の場合、内容理解が難しいこともあります。
そのため、わかりやすい言葉・図解・説明補助を活用して理解を確認しましょう。
場合によっては家族や後見人の同意を併せて取得します。
同意は「いつでも撤回可能」であることを明示し、撤回があった場合の対応(HP削除・掲示撤去など)を迅速に行う体制を整えておきましょう。
高槻市や茨木市、枚方市などでは、行政指導や運営指導時に「個人情報保護」「同意書管理」の確認が強化されています。
介護・障害福祉に精通した行政書士に依頼すれば、以下のようなサポートが可能です。
「個人情報保護」と「利用者の尊厳」は、福祉サービス運営の根幹です。
写真撮影一つをとっても、適切な同意取得とルール整備が事業所の信頼につながります。
重要なのは、
小さな配慮が、大きなトラブル防止につながります。
個人情報保護や写真撮影同意書の作成・見直しをご検討の際は、
介護・障害福祉専門の行政書士にご相談ください。
現場運用と法令基準の両面から、最適な文書整備をサポートいたします。
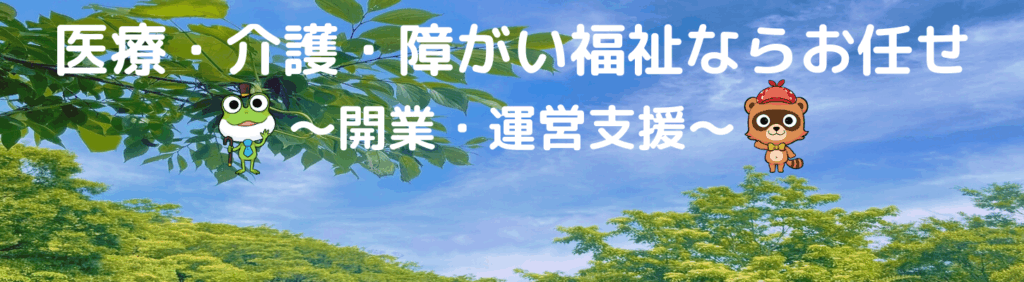
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。