
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


介護・障がい福祉事業所では、「虐待防止委員会」「身体拘束適正化委員会」など、重大な権利擁護に関わる委員会の設置が義務づけられています。
しかし、現場を数多く支援していると、次のような声を聞くことが少なくありません。
つまり、“委員会の形骸化”が静かに進んでいるのです。
この記事では、高槻市で介護・障がい福祉分野を専門とする行政書士の立場から、本当に機能する委員会運営のポイントをわかりやすくお伝えします。
委員会が表面的な運営に陥る主な理由は以下です。
月1回の開催、議事録の作成──形式的に義務を果たすことがゴールになり、
中身の議論が空洞化してしまうケースが多くあります。
「なんとなく参加している」状態だと、意見は出てきません。
とくに、現場職員が「責任を負うのが怖い」と感じると発言が減りがちです。
虐待防止や身体拘束に関する基準は複雑で、
制度理解が不十分だと、改善策を考えること自体が難しいのが現実です。
本来はヒヤリ・事故・苦情などの情報が委員会で分析されるべきなのに、
情報共有が不十分で“議題がない”状態になりがちです。
いずれも共通しているのは、「現場の課題を“見える化”し、改善につなげる組織」であること。
書類づくりを目的とする場ではありません。
虐待・身体拘束の議題は、重大な事例だけではありません。
これらの小さなサインを議題にできる委員会が、虐待防止にも強くなります。
改善策は「思いつき」ではなく、仮説 → 実施 → 評価 → 再検討の流れが重要。
委員会で
「なぜこの行動が起きたのか?」
「どんな環境要因があるのか?」
「職員の関わり方はどうか?」
という“原因分析”を行いましょう。
現場で起こる不適切ケアの多くは、
業務負担・人間関係・感情労働の蓄積から生まれます。
委員会で次を扱うと大きく変わります。
拘束ゼロの体制構築には、代替方法のアイデア蓄積が不可欠です。
例:
委員会で職員の成功事例を共有し続けると、拘束ゼロに近づきます。
ヒヤリ・苦情・事故・不適切ケアの情報を、
委員会と管理者が一元管理すると、次が見えてきます。
データに基づく改善は、
運営指導(実地指導)にも非常に強い組織づくりにつながります。
担当者だけに責任が集中しないようにすると、議論が広がります。
何を確認すべきかが明確になり、形式的な会議を防ぎます。
ただのメモではなく、
**「改善の履歴」**として残すと、委員会の価値が上がります。
10分程度のミニ研修(不適切ケア・制度解説・事例紹介など)を毎回実施すると、
委員のスキルが底上げされ、発言が増えます。
虐待防止や身体拘束の委員会は、
運営指導で最も見られるポイントであり、
利用者の権利擁護・職員の働きやすさ・事業所のリスクマネジメントすべてにつながる重要な仕組みです。
形骸化していると、
しかし、逆に言えば、
委員会を“本当に機能させる”ことができれば、事業所は劇的に強くなります。
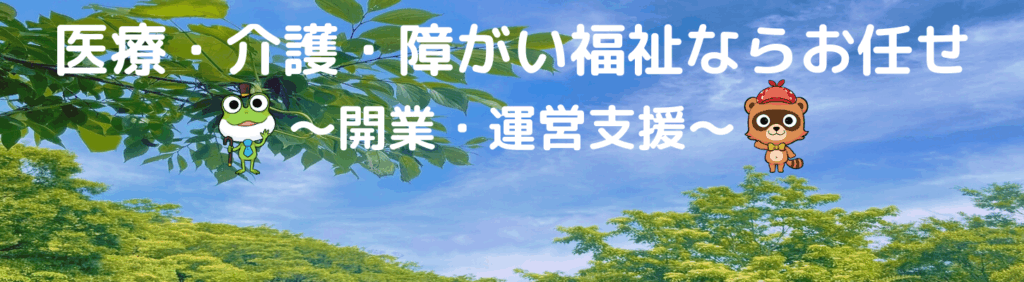
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。