
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


介護・障がい福祉の現場では、虐待防止、身体拘束適正化、感染対策など、
多くの研修が“義務”として課せられています。
しかし、現場を支援しているとこんな声をよく耳にします。
つまり、義務として“こなすだけの研修”になっているのです。
この記事では、介護・障がい福祉専門の行政書士として、
研修設計のポイントを“行政対応”“行動変容”“現場実装”の観点でわかりやすく解説します。
原因の多くは、次の3つに集約されます。
制度やルールを伝えるだけでは、人は行動を変えません。
“分かっているけど、できない”状態が続きます。
研修は“単発のイベント”になりがちです。
現場に落とし込む仕組みがなければ、定着は生まれません。
「虐待防止研修をする」
「個人情報研修をする」
だけでは、目標が不明確です。
目的のない研修=義務感の研修になります。
研修を「やらされるもの」から「組織の力になるもの」へ変えるために、
以下の3ステップが有効です。
研修設計でもっとも重要なのは、
「この研修のあと、職員にどんな行動をしてほしいか?」
を明確にすることです。
例:虐待防止研修
例:身体拘束適正化研修
行動基準を研修の前に設計することで、現場に落とし込みやすくなります。
現場で起きたヒヤリ、苦情、不適切ケア──これらは最高の教材です。
と問いかけることで、“自分ごと化”が進みます。
座学だけでは行動は変わりません。
短時間で良いので、体験型学習を1つ入れるだけで効果が倍になります。
研修内容は、必ず組織の理念や支援方針と紐づけましょう。
例:
「自立支援の理念にもとづけば、こういう声かけに変わります」
「尊厳の視点では、この対応の何が問題でしょうか?」
理念を“実務で使う力”が育ちます。
研修のポイントを、次の職員会議でふり返る仕組みを作りましょう。
「研修で学んだことのうち、実践してみたことはありますか?」
と質問するだけでも効果が大きいです。
行動の定着には“見える化”が欠かせません。
これらをチェックリスト化すると、研修で学んだ内容が日常化します。
虐待防止委員会・身体拘束委員会・リスク管理委員会は、
研修内容の実装を確認する最高の場所です。
委員会で次のように扱うと効果的です。
委員会と研修が連動した瞬間、
研修は“義務”から“価値”へ変わります。
運営指導(実地指導)では、
研修は“実施したか”ではなく
“事業所の行動に反映されているか”
が見られます。
次の3つが揃えば、行政対応にも強い事業所になります。
行政書士として支援している事業所でも、
この仕組みを作った事で指摘が激減した例が多くあります。
研修は義務ではありますが、
義務だけでは終わらせてはいけません。
研修は、
・職員の質を高め
・利用者の安全を守り
・管理者を支え
・組織を強くする
“価値ある仕組み”に変えることができます。
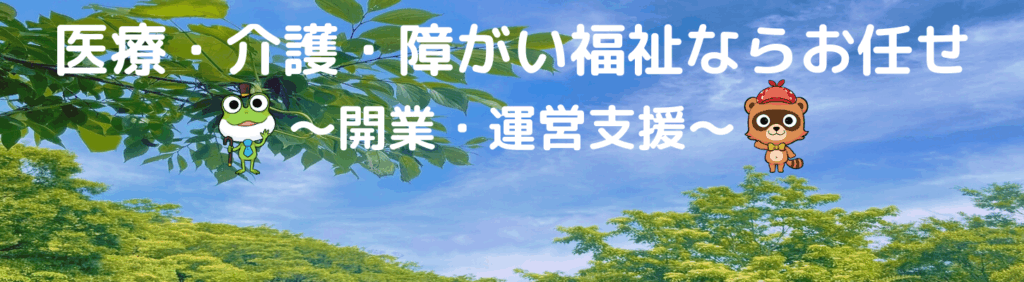
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。