
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


介護・障がい福祉事業所における「身体拘束」は、原則禁止であり、例外的に認められる場合でも 「非代替性・切迫性・一時性」 であることが求められています。
その適正運用を確認する仕組みが 「身体拘束適正化委員会」 です。
運営指導でも 設置・開催・記録の有無が必ず確認される項目 のひとつとなっています。
この記事では、
✅ 身体拘束適正化委員会とは何か
✅ どのように設置し、運営すべきか
✅ 必要な書類や運営指導で見られるポイント
をわかりやすく解説します。
身体拘束の廃止および適正化を継続的に推進するために、介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法で設置が求められている委員会です。
介護保険では 「身体拘束の適正化のための委員会」を設置すること が義務。
障がい福祉サービスでもガイドライン等で求められています。
大阪府・高槻市の運営指導で必ず確認される内容:
身体拘束は利用者の尊厳に直結するため、法人のリスク管理にも関係します。
| 役割 | 想定メンバー |
|---|---|
| 委員長 | 管理者・施設長 |
| 委員 | 介護職員代表、看護師、生活相談員、サービス提供責任者 等 |
| 外部委員(任意) | 家族代表、虐待防止委員会との兼任、医師など |
※小規模事業所でも「形だけ」ではなく、検討・改善ができる体制が必要。
✅ 年4回以上(実地指導で確認される最低ライン)
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 身体拘束適正化指針 | 組織としての基本方針(必須) |
| 身体拘束適正化委員会規程 | 委員会設置の根拠書類 |
| 議事録 | 開催証拠(署名・日付は必須) |
| 身体拘束に関する記録様式 | 例外的拘束の理由・時間・代替策等 |
| 職員研修記録 | 出席簿・研修内容 |
| 身体拘束ゼロ実践計画書 | 任意だが運営指導で有効 |
| 指摘例 | 対応策 |
|---|---|
| 委員会が開催されていない | 年4回の定例開催化・年間スケジュール化 |
| 議事録に署名・日付・参加者が無い | 様式統一+管理者チェック |
| 指針が古い or 存在しない | 年1回以上の見直しを記録 |
| 研修が未実施 | 委員会主催で年1回以上開催 |
| 身体拘束の判断が職員任せ | 委員会で事前検討+記録の見直し |
✅ 身体拘束適正化指針・規程テンプレート提供
✅ 委員会議事録・年間計画書の作成支援
✅ 実地指導対策チェック
✅ 職員研修(身体拘束×人権)資料作成
✅ 委員会の実施
高槻市・北摂エリアで
「委員会の作り方がわからない…」
「書類・規程・議事録を整えたい…」「委員会に参加してほしい…」
といった事業所様はお気軽にご相談ください。
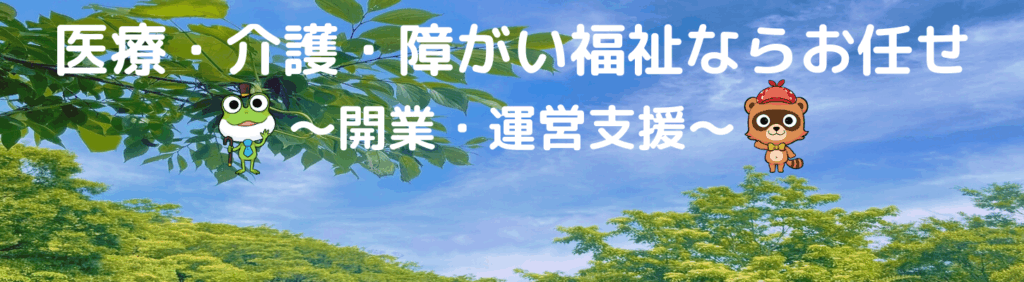
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。