
-
お電話でのお問い合わせ072-691-5370
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ072-691-5370


介護・障がい福祉事業所において、管理者は組織の要(かなめ)です。
人材配置、職員育成、利用者対応、行政とのやり取り、請求、委員会運営、監査対応──
多岐にわたる業務を担い、日々“判断”の連続にさらされています。
しかし、その管理者ほど、
最も孤立しやすい立場であることをご存じでしょうか。
現場を訪問していると、管理者の方からこうした声をよく聞きます。
管理者の孤立は、事業所の質低下・離職増加・不適切ケアの温床につながる重大な問題です。
この記事では、介護・障がい福祉専門の行政書士として、
“管理者が孤立しないための仕組み”
“組織を守る外部の目の役割”
についてわかりやすく解説します。
管理者は常に
など、組織の“最終判断”を求められます。
失敗できないというプレッシャーが、
相談を難しくさせてしまいます。
管理者は職員から“評価する側”として見られがちです。
そのため、
といった状況に陥りやすいのです。
障害者総合支援法・介護保険法・行政手続き・運営指導・報酬改定…
制度の変更は多岐にわたり、把握するだけでも大変です。
「何が正しいのかわからない」
と感じても不思議ではありません。
管理者の仕事は、外部から見えにくい領域が多いため、
“独りよがりな運営”になってしまうことがあります。
外からの助言がないと、
が進行しやすい環境でもあります。
管理者の孤立は、組織全体に深刻な影響を与えます。
判断が偏ると、不適切ケアに気づきにくくなり、
虐待防止委員会や身体拘束委員会が形骸化する危険があります。
管理者の余裕のなさは、
“孤独な判断”は、
法令解釈の誤り・運営規程違反・記録不備などにつながります。
最悪の場合、行政処分につながることもあります。
管理者の孤立を防ぎ、組織を支えるために重要なのが、
*外部の目(External Eyes)”です。
ここでいう外部の目とは、
事業所の中にいない専門家が、第三者として助言する仕組みを指します。
外部の目は、主に次の3つの効果を生みます。
運営で迷ったとき、外部専門家は
管理者は
「一人で決めなくていい」という安心感が得られます。
外部の目は、事業所内部では気づけない課題を見つけられます。
内部だけで運営していると、
“慣れ”によって見えなくなる部分を補ってくれます。
外部専門家が継続的に関わることで、管理者は
といった状態になります。
管理者にとって、
“話せる相手がいる”ことは何よりの支えになります。
介護・障がい福祉に特化した行政書士は、
単なる書類作成者ではありません。
むしろ、“事業所運営の伴走者”として機能できます。
管理者が安心して業務に専念できる体制づくりを支えます。
管理者が孤立しないことは、
利用者の安全・職員の定着・運営の安定──
すべての基盤となります。
管理者は組織の要。
しかし、要が折れてしまえば組織は崩れます。
だからこそ、
“外部の目”という第三者の存在が必要なのです。
外部専門家を活用することで、
管理者は「一人で抱え込む」状態から解放され、
組織はより健全で強固なものになります。
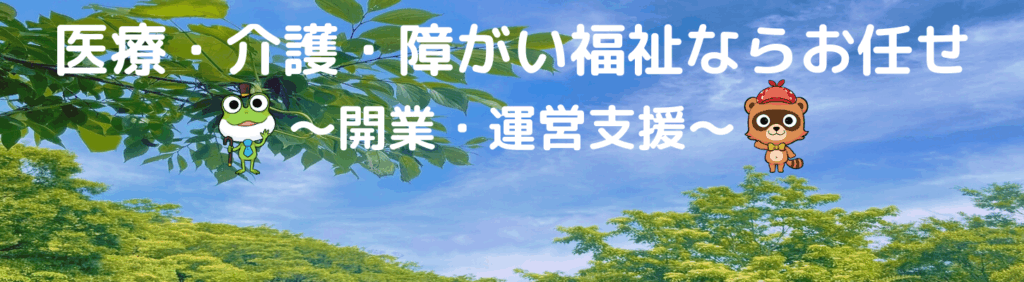
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。